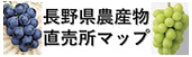投稿日:
更新日:
春の野山は幸せいっぱい!信州の山菜で感じる大地の息吹

南信州独特の食文化を伝える山菜「おこぎ」

一般的には「ウコギ」の名で知られており、「おこぎ」は飯田地域ならではの呼び方です。
野村 慶一さん
だんだんと里山の雪も解け始める3月上旬頃から、長野県では農産物直売所や道の駅、スーパーなどで地元の人々が収穫した山菜を見かけるようになります。
大地を感じる風味や独特のえぐみ、ほろ苦さを持つものも多い山菜。これはポリフェノールや植物性アルカロイドなどによるもので、春の訪れを感じさせてくれるだけではなく、寒く厳しい冬を乗り越えるため体温を逃さないようにと脂肪をため込みやすい状態になっていた私たちの冬の体から老廃物を排出し、春に向けて活動的な体へと切り替える手助けをしてくれるのだとか。「春の皿には苦味を盛れ」※ということわざもあるほど、春に山菜を食べることは理にかなったことだとされているのです。

「旬が過ぎて大きくなってしまった『おこぎ』でも、天ぷらやかき揚げにするとサクサクとした食感でおいしいですよ」と野村さん
冬眠から目覚めたクマが初めに口にするともいわれる「フキノトウ」をはじめ、「コゴミ」「タラノメ」「ワラビ」「フキ」「ウド」「根曲り竹」など、長野県の野山は春から初夏にかけ、さまざまな山菜であふれますが、中には特定の地域でしか食されていないようなものも。そのひとつが、春の新芽が芽吹く頃、南信州でいち早く春の訪れを感じさせる「おこぎ(ウコギ)」。1.5~2mほどの高さのウコギ科の灌木の若芽で、渋みやほろ苦さを感じる味わいや、シャキシャキとした歯触り、鮮やかな緑色が特徴です。全国に自生していますが、食用とされているのは、主にヤマウコギが食される飯田・下伊那地方と、江戸時代に米沢藩第9代藩主・上杉鷹山公が飢饉に備えてヒメウコギを生垣に植えるよう奨励したとの話も残る山形県置賜地方のみともいわれます。
飯田・下伊那地方で「おこぎ」を食べる文化が根付いた理由は定かではありませんが、昔から各家庭で畑や庭先、土手などに生えているものが収穫され食べられており、2000年代前半から地域に直売所が増えてきたことで市場にも流通されるようになりました。

おこぎのハウス栽培を手がける農家は飯田市内でもわずか。一芽ずつ丁寧に収穫していきます。
そんな「おこぎ」を昔から露地栽培し、さらに25年ほど前からはハウスでの栽培を始め、地域でもいち早く直売所に出荷しているのが、飯田市の野村慶一さんです。太陽からの自然の熱を利用して暖めたハウスの中で、自宅の裏山から湧き出る湧水を張ったバケツに幹をさして栽培し、例年3月に入った頃から1~2cmほどのサイズになった若芽を摘んでいきます。小さな芽のほうが柔らかくて食べやすく、また、ハウス栽培のほうが露地ものより柔らかいとのこと。「おこぎの幹には鋭い小さなトゲがあるので、柔らかいうちに丈夫な革の手袋で幹をしごき、全部取ってしまうのがポイントです」と野村さん。ハウスものは3月上旬、露地ものは4月上旬から出荷が始まります。旬はゴールデンウィークまで。芽が大きくなるとキシキシという独特の歯触りが生じてしまうのだとか。

栽培に使用する湧水は名水百選にも選定されている「猿庫の泉」と同じ水系とのこと。
定番の食べ方は、沸騰したお湯に5秒ほどくぐらせ、鰹節と醤油をかけるおひたしですが、炒めものや和えもののほか、茹でた若芽を塩揉みして刻み、炊きたてご飯に混ぜてもおいしく味わえます。茹でたものを冷凍保存すれば長期間「おこぎ」を楽しむことも。

JAみなみ信州が運営する「およりてふぁーむ農産物直売所」。地域の農産物を豊富に取り扱っており、野村さんも「おこぎ」のほか、山菜は「タラノメ」「コゴミ」「タケノコ」「ウド」なども「およりてふぁーむ」へ出荷しています。
「春を代表する山菜の『コゴミ』も、この辺でも自生していますが、盛んに食べるようになったのはここ15年くらいのことだと思います。それも、この地域には『おこぎ』を食べる文化が根付いていたからかもしれませんね」と野村さん。山菜採りは地域に根ざした文化としての側面もありますし、日ごと様子が変わる春の山野で収穫期を逃すと、あっという間に旬を過ぎてしまう儚(はかな)さもあります。山菜から地域に脈々と受け継がれてきた文化を感じ、その地域ならではの旬を味わってみませんか。
※春の食事には春らしい食事を食べようとの意味。苦味は山菜や春野菜を指す。
[およりてふぁーむ農産物直売所]
飯田市鼎東鼎281 TEL 0265-56-2822
http://www.ja-mis.iijan.or.jp/directsales/store.php
北信州を代表する山の恵み「根曲り竹」

地面から顔を出す「根曲り竹」。野沢温泉村のほか、山ノ内町志賀高原、高山村なども北信地域有数の産地として知られています。
お宿まるとや 女将
富井 明美さん
山菜シーズンも終盤に差しかかる5月から6月下旬にかけて収獲時期を迎えるのが「根曲り竹」。北信州の人々が愛してやまない山の恵みのひとつです。山陰、信越、東北、北海道の日本海側、標高1,000m前後の山地に生育する「チシマザサ」とよばれる大型の笹の若芽で、スーパーなどで見かけることも多い孟宗竹と比べると、スラっとした形状が特徴です。山陰では「姫竹」、山形では「月山竹」など、各地域でよび方が異なり、雪深い長野県の北信地域では、雪に押されて根元が曲がって出てくることから「根曲り竹」の名で親しまれています。

「竹の子汁」は北信地域のソウルフード。その味や作り方は各家庭で引き継がれてきました。
えぐみが少なくほのかに甘みを感じる味わいと、ほどよい弾力がありながらも歯切れのよい食感が特徴。アクが少ないので採れたてのものは下茹ですることなく調理可能で、煮物や、天ぷら、素焼きなど、さまざまな食べ方でその味を楽しめます。中でも北信州の郷土料理として知られているのが、「根曲り竹」に味噌、そしてサバの水煮缶を加えた味噌汁「竹の子汁」です。

「根曲り竹」の皮の剥き方も教えてくれた富井さん。頭の部分を折ってからくるくる指に巻き付けるように剥いていくとのこと。コツが必要です。
「最初は細い竹の子にも、味噌汁にサバ缶が入ることにもとても驚きました。魚臭くないのかしらと、おそるおそる食べてみると、柔らかく、アクが少なくて、何よりサバ缶の塩気や油分と『根曲り竹』や味噌の相性がよく、とてもおいしかったんです」と話すのは長野県東部に位置する小海町から野沢温泉村へ嫁ぎ、温泉旅館「お宿まるとや」の女将を務める富井明美さんです。

近隣の道の駅で販売されている「根曲り竹」。近くにサバの水煮缶も販売されていました。
野沢温泉村や山ノ内町など、「根曲り竹」が採れる地域では、スーパーの一角にサバ缶コーナーができるほどで、富井さんも季節になると箱買いするのだとか。それほど、サバの水煮缶と「根曲り竹」は最高の組み合わせで、北信地域の初夏の食卓に欠かせません。
時期になると、近隣の道の駅などで「根曲り竹」を購入することも可能ですが、自ら山に入る人も多く、野沢温泉村では地区ごとに参加者を募って「根曲り竹」の竹の子狩りを行っており、富井さんも毎年参加しているそう。傾斜のある斜面を背丈ほどもある竹を泳ぐようにかき分けながら、笹やぶの根元に生える「根曲り竹」を探すのはとても重労働で、鋭い竹や笹で肌や洋服が切れてしまうこともしばしば。また、「根曲り竹」はクマの好物でもあるので、野生のクマと遭遇しないようクマ除けの鈴も欠かせません。

富井さんお手製の「根曲り竹の穂先の天ぷら」と「根曲り竹と身欠きニシンの煮物」。天ぷらは粉チーズを混ぜて揚げても、味に深みやコクがでておいしいのだとか。
収穫した「根曲り竹」はどんどんと固くなってしまうため、採ってきた日のうちに調理や下処理を行うことがポイント。富井さんは採ってきた「根曲り竹」を、「竹の子汁」はもちろん、煮物や、穂先の天ぷらのほか、焼き竹の子、炊き込みごはんなどに調理し、宿泊客にも振る舞います。煮物には凍り豆腐も加えるのが富井さん流。水で戻した凍り豆腐を素揚げし、竹の子、身欠きニシンと煮ると、油を吸った凍り豆腐が味わいを深くするといいます。

収穫後すぐに食べられない場合は、採れた日に皮を剥き、茹でて、茹で汁ごと冷蔵庫で保存しておくとよいとのことです。
それでも「やっぱりおすすめの食べ方は『竹の子汁』」と富井さん。具材や作り方は各家庭で異なりますが、基本の「根曲り竹」とサバの水煮缶に、豆腐や豚肉などを加えてもおいしいそうです。宿泊客にも好評で、料理を目当てに毎年「お宿まるとや」を訪れる人も少なくありません。
ソムリエの資格も持つ富井さん。「地域の郷土食にはやっぱり地域の地酒が合います。日本酒もよいですが、『根曲り竹』の料理には、近隣の高山村で醸されるシャルドネなど軽快な白ワインも合うんですよ」と教えてくれました。ワインと「根曲り竹」の新感覚の相性も楽しんでみてはいかがでしょうか。
銀座NAGANOで買える
「根曲り竹」とサバ缶を使った「竹の子汁」のレトルトパウチを銀座NAGANOでも販売中!まずはその味をお試しいただき、「根曲り竹」の季節には採れたてを食べにお越しください。
銀座NAGANOでは旬の山菜も販売しています。季節になったら根曲り竹も入荷予定!
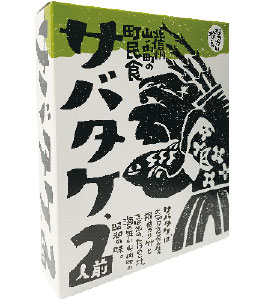
サバタケ
250g×2 1,199円
[山ノ内町総合開発公社]

鯖のたけのこ汁
170g 540円
[タカ商(長野市)]
[お宿まるとや]
下高井郡野沢温泉村豊郷9798 TEL 0269-85-2235
https://kt2062390.wixsite.com/marutoya

山菜採りハイキングはいかがでしょうか?
旬の山の幸に出合う山菜採り体験はいかがでしょうか。信濃町のサンデープランニングLAMPでは、野尻湖周辺の野山を探索し、約50種類の山菜を収穫する「山菜採りハイキング」を開催予定。ベテランガイドが春の山へとご案内します。採ってきた山菜はレストランのシェフが腕をふるい、豪勢な山菜づくしディナーへと変貌します。自分で収穫した山菜の味わいは格別ですよ!
[期間]4月17日~6月13日(予定)
この記事は2021年3月時点の情報です。
取扱商品等は変更になっている場合がございますので、ご了承ください。