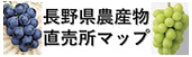投稿日:
更新日:
信州の肉を喰らう!第2弾

海のないぶん、地域ごとにさまざまな食肉文化が育まれてきた長野県。めん羊飼養からつながる羊肉(マトン)文化やジンギスカン、農耕馬がもとになった馬肉文化、内臓食など、各地に根付く食肉文化をお届けする第二弾です。
Vol.1 “ひつじの町”が守る羊肉文化の伝統と情熱
Vol.2 焼肉日本一!南信州で楽しむ羊肉や内臓食の魅力
Vol.3 明治創業の老舗が伝える温故知新の郷土の味
vol.1 “ひつじの町”信州新町が守る羊肉文化の伝統と情熱

信州不動温泉さぎり荘
所長 小山 宙軌(ひろき)さん

日本では戦前、軍需目的でめん羊飼養が国策として全国に奨励され、長野県内でも盛んに飼育が行われました。ここから根付いたのが羊肉(マトン)を食べる文化です。実は長野県は北海道に並ぶ“ジンギスカン王国”として知られています。

しかし現在、国内に流通している羊肉の99%以上は輸入肉。国産羊肉は希少になった今でも地域をあげて羊を育てているのが、“ひつじの町”として知られる長野市信州新町です。地域内の国道19号沿いにはジンギスカンを提供する専門店が並び「ジンギスカン街道」とよばれ、地域一体となって羊肉文化を盛り上げています。

この地で羊毛を取るための羊の飼育が始まったのは、昭和5(1930)年。冷涼で乾燥した気候が飼育に適していたことに加え、かつて盛んだった養蚕の残りかすと豆殻などが飼料となったことで、羊を飼う農家が増え続けました。昭和20年代後半には、地域に4,000頭もの羊がいたと言われています。
昭和11(1936)年に料理講習会でタレを漬け込んだ味付けジンギスカンのおいしさが認知され、昭和26(1951)年には観光協会がジンギスカンで来客をもてなしたことで、信州新町の羊肉の評判が一層広まりました。
ところが、昭和30年頃からは化学繊維の台頭で畜産家が激減。昭和40~50年代には交通の便が良くなり、人々の往来の増加とともにジンギスカン料理店が増えたにも関わらず、町にはほぼ羊がいなくなってしまったのです。

▲平成22(2010)年に信州新町が長野市と合併したことで、市の指定管理施設に移行した「さぎり荘」。温泉宿だが、日帰り入浴や食事だけの利用も可能
地元産の羊肉をなんとか再興しようと、昭和57(1982)年に導入されたのが、食肉用のサフォーク種でした。今まで町で育てていた羊毛を刈るためのコリデール種やメリノー種と異なり、羊肉をとるために特化し改良されたイギリス原産の肉用種で、顔が黒いのが特徴です。
この信州新町産のサフォーク肉が食べられる地域唯一の食事処として、食通にも親しまれているのが、昭和48(1973)年に町営施設として創業した「信州不動温泉 さぎり荘」。「ジンギスカン街道」のもっとも西側に位置する保養施設です。

こだわりは、ラム(子羊)とマトン(2歳以上)の間である1~2歳の「ホゲット」のサフォークを提供していること。
「牛とも豚とも違う、羊肉本来の旨みや脂の癖のなさ、柔らかさといった魅力をもつのがホゲットです。“ひつじの町”を売りにしている以上、羊肉のよさがもっとも伝わるホゲットを提供しています」
こう話すのが、所長の小山宙軌さんです。近年は生産者の高齢化とコロナ禍により、地域内のサフォークの飼育頭数がより減少したことから、「さぎり荘」では一念発起し、2021年から旧町営牧場を活用して約160頭のサフォークの飼育も始めました。

▲地域の道の駅「信州新町」には特設のジンギスカン販売コーナーも
「羊は放牧のイメージですが、当社では和牛のように畜舎で管理し、乾燥牧草や穀物、ビール糟やおから、りんご等を与えて育てています。青草由来のえぐみや臭さが全くなく、肉が本当にうまいんですよね」
生まれも育ちも信州新町の小山さん。サフォークは昔から特別なときしか食べられない貴重なものでしたが、輸入羊肉を味付けしたジンギスカンは「焼き肉といえばジンギスカンだった」と話すほど、家庭でよく食べていたそうです。

▲「さぎり荘」で提供しているジンギスカンと地元産サフォークの盛り合わせ
信州新町のジンギスカンの特徴は、あらかじめ肉にタレを漬け込んでいること。「ジンギスカン街道」にある10店舗にはそれぞれに特製のタレがあり、濃いめの味付けが多いそうですが、「さぎり荘」では羊肉そのものをしっかりと味わえるよう、醤油ベースにニンニクやショウガ、すりおろしりんごと玉ねぎなど14種類を調合してマイルドに仕上げています。この特製ダレのジンギスカンが味わえるのも「さぎり荘」の魅力です。

▲地域の道の駅「信州新町」には特設のジンギスカン販売コーナーも
なお、羊肉はレアでも食べられるそうですが「しっかりと焼いたほうが余分な脂が適度に落ちるのでおすすめ」と小山さん。サフォークも焼きすぎない程度に焼き、岩塩でシンプルに味わいます。これにより、噛めば噛むほど味わい深い羊肉特有のおいしさをじっくりと堪能することができるのです。
「食肉用の改良品種であるサフォークは出産や育児が不得手で、寄生虫感染など飼育の難しさもありますが、羊は信州新町の文化ですし、肉のうまさは一級品。遠方から食べにきてくれるリピーターも少なくありません。地域の強みを生かした食材として、これからもこの食文化を残していきたいですね」
土地の歴史と文化を伝えるサフォークとジンギスカン。小山さんの言葉から、その伝統を守る者としての矜持と熱意が伝わってきます。

信州不動温泉さぎり荘
住所:長野市信州新町日原西300-1
電話:026-264-2103
http://www.sagirisou.com/
※この記事は2022年12月時点の情報です。取扱商品等は変更になっている場合がございますので、ご了承ください
vol.2 焼肉日本一!南信州で楽しむ羊肉や内臓食の魅力

飯田市広報ブランド推進課 市瀬 智章さん
南信州畜産物ブランド推進協議会 平沢 真一さん

▲南信州の良質で特徴ある食肉文化を広くPRする「南信州畜産物ブランド推進協議会」の平沢真一さん
南信州もまた、古くからめん羊飼育による羊肉文化が根付く土地。特に飯田市は人口1万人当たりの焼肉店数が全国一の“日本一の焼肉の街”として知られ、どの店にもほぼマトンが並んでいます。
「この地域では全国で高い評価を受ける南信州牛や数多くの銘柄豚など畜産が盛んですが、“飯田焼肉”は羊から始まったと言われています。今では店で提供される羊肉は輸入物になりましたが、もとは羊毛の生産が盛んで、老齢になった羊をタンパク源として食べていたことから羊を食べる文化が根付いています」
こう話すのは、飯田市農業課で「南信州畜産物ブランド推進協議会」事務局の平沢真一さんです。

▲「マトンやジンギスカンは市民にとっておなじみの肉」と話す飯田市広報ブランド推進課の市瀬智章さん
また、「マトンの独特の風味が苦手な人もいると思いますが、飯田市民は焼肉店でマトンを注文しない人はいないというほど好んでよく食べます。それは、昔から地域で食べられてきたからです」と語るのは、飯田市広報ブランド推進課の市瀬智章さん。
そのマトンからつながる焼肉文化は、精肉店では電話一本で焼肉道具セットを運ぶ「出前焼肉」のサービスがあるほど地域に根づいています。

▲マトンは南信州の焼肉で外せないメニュー
この地でマトン(ジンギスカン)が流通した背景は諸説ありますが、一説によると、昭和10〜20年代にこの地域に来ていた朝鮮半島の人々が、唐辛子やニンニクから作った独自のタレを揉み込んだ家畜の羊肉を焼いて食べていたことにあるそう。それまで地域では、肉は鍋で煮て食べるのが主流だったそうですが、ここから羊肉をタレに漬け込んで焼く文化が広がったと言われています。

家庭で焼肉を食べる文化が根付くとともに、昭和20年代から焼肉店が地域内に徐々に増えていきました。今やスポーツ大会や運動会といった行事、草刈り等の作業の慰労会、懇親会などのほか、飯田下伊那地域で活発な公民館活動など人々が集まるさまざまな場面で、飯田市では焼肉がセットで行われるのが定番です。
また、コロナ禍以前の飲み会では一次会で焼肉店に行き、二次会を経て夜も更けたころ、締めとなる三次会でも焼肉店に行くことが多かったとか。遅い時間まで営業している焼肉店が多いのも、焼肉文化が根付くこの地域ならではです。

▲2022年11月29日の「飯田焼肉の日」にオープンした「信州飯田焼肉研究所」
しかし、市民にとって焼肉はあまりに身近だったことから、“日本一の焼肉の街”であることは、意外にも行政でも明確に把握していなかったそう。認識されたきっかけは、ひょんなことからでした。
2011年に開催された自治体職員研修会で親交が生まれた北海道美幌町の職員から、翌2012年に北海道新聞が掲載した記事の情報提供を受けたのです。北海道北見市の焼肉特集で、人口1万人当たりの焼肉店舗数が全国では飯田市についで2番目、つまり飯田市が1位と紹介されていたのです。
その後、2015年に「南信州牛ブランド推進協議会(現南信州畜産物ブランド推進協議会」がタウンページの情報を検証。飯田市が全国1位であることを正式に確認し、公表しました。以降、“日本一の焼肉の街”として、地域内外の各メディアに取り上げられることになりました。
2020年には、飯田下伊那食肉組合(現南信州食肉組合)と地域のマルマン株式会社が日本記念日協会に申請し、11月29日を「飯田焼肉の日」に制定。2021年に市民有志の飯田焼肉世界記録挑戦実行委員会が11m29cmの鉄板で焼肉をし、“世界一長い鉄板”が世界記録に認定されました。
そして、2022年、株式会社信州セキュアフーズが市内中心部に「信州飯田焼肉研究所」を設立。焼肉店の情報発信や加工品の販売、飯田の焼肉の歴史資料や“世界一長い鉄板”の展示などを行う新拠点として、早朝6時から深夜24時まで営業しています。行政主導ではなく、民間企業が率先して地域の文化をリードしているのも“飯田焼肉”の特徴です。

▲牛の内臓の黒皮まで食す「黒モツ」は現地を訪れないと味わえないメニュー。ボイルして提供され、好みの食感まで鉄板で焼く
また、内臓食(ホルモン)も飯田焼肉の魅力です。地域にはかつてと畜場があり、新鮮な内臓が入手しやすかったことから、「黒モツ」など他地域では見られないような内臓部位や、ホルモンを茹でた「茹でホル(茹でおた)」などの独自のメニューが焼肉店に名を連ねています。

そんな焼肉激戦区の飯田市内でも、南信州牛とともにマトンや「黒モツ」など昔ながらの飯田焼肉の両方が味わえるのが「和牛一頭買い ふえ門」です。南信州牛は主に関西に流通しており、地元ではなかなか味わえなかったなか、同店では国産牛の最高等級であるA5ランクに認定された南信州牛のみを一頭買いして提供。トレーサビリティを確立するとともに、貴重な部位も豊富に揃えています。

▲牛の内臓の黒皮まで食す「黒モツ」は現地を訪れないと味わえないメニュー。ボイルして提供され、好みの食感まで鉄板で焼く
そんな「ふえ門」の特徴はタレにも見られます。飯田市では「各家庭に秘伝のタレがある」と言われるほど焼肉のタレにこだわりをもつ人が多くいますが、同店では辛口と甘口の2種類を用意。どちらもたまり醤油のブレンドがベースで、辛口は飯田市内の焼肉店に多く見られるニンニクを効かせている一方、甘口は南信州のフルーツを使い、ニンニクは使っていません。

▲週3日は焼肉を食べるというほどの焼肉好きが高じて2018年に「ふえ門」をオープンした佐々木さん
「辛口のタレは『黒モツ』などの内臓系やマトンによく合い、甘口は牛肉のおいしさが際立ちます。ただ、内臓系でもシマチョウなど脂が多いホルモンは甘口のタレにネギやニンニクを加えるのがおすすめですね」
こう話すのは、代表の佐々木 博さん。最近の一番人気メニューはミックスホルモンですが、南信州牛を目当てに訪れる人からは、上カルビの盛り合わせやリブロース、上ハラミなども好評だと言います。また、牛タンの最高級部位「タン元」は、厚切り牛タンの柔らかさとジューシーさを堪能でき、ファンが多い一品です。
「やはり南信州牛はうまいですね。どの肉も牛脂を敷いて焼いたほうがおいしいですし、厚めの肉はじっくりと焼いてください」

▲「ふえ門」の人気メニューのひとつ「ミックスホルモン」
近年は「せっかく飯田を訪れたなら南信州牛を食べたい」と、県外からも多くの人が訪れるという同店。“飯田焼肉”の豊かなバラエティに彩りを添えています。

「飲食店や事業者の皆さんと市民、行政が協力し、“焼肉の街”を一段と盛り上げていきたい」と市瀬さんと平沢さん。行政としては、同様に焼肉店が多い北海道北見市など他県の自治体とも協力し合うことで、市内外のつながりから飯田の焼肉文化をPRしていきたいと意気込んでいます。
南信州畜産物ブランド推進協議会
住所:飯田市鼎東鼎281 飯田市農業課生産振興係内
電話:0265-21-3217
https://msgyu.com/
和牛一頭買い ふえ門
住所:飯田市銀座3-1-1 トップヒルズ銀座1F
電話:0265-52-9029
https://fuemon.com/
※この記事は2022年10月時点の情報です。取扱商品等は変更になっている場合がございますので、ご了承ください
vol.3 明治創業の老舗が伝える温故知新の郷土の味

満津田食堂
松田 道彦さん・真理子さん

▲馬肉を食べる文化は長野県内各地に根付きますが、「おたぐり」が食べられるのは南信州のみ。味噌味・塩味・醤油味など店によって味付けはさまざま
南信州の食肉文化は、焼肉だけに尽きません。南信州は農耕馬の産地でもあったことから、馬肉料理が浸透しているのも特徴です。特に馬の腸をじっくり煮込んだモツ煮「おたぐり」が食べられるのは、この地域ならでは。草食動物である馬の長い腸を洗う際、たぐり寄せたことが料理名の由来で、独特の風味があるので好き嫌いが分かれますが、地元では酒のつまみとして好んで食べる人が多いそうです。

そんな「おたぐり」を提供する老舗料理店が、明治20(1887)年創業の「満津田食堂」。明治時代に発生した大火で市街地の多くの飲食店が移転してしまったなか、同店は今も創業当時から変わらぬ場所で営業を続けています。

「長年、鯉料理専門店でしたが、地元の需要に応え、先代の父が少しずつ飯田・下伊那地域でしか味わえない料理を提供するようになりました」
こう話すのは、5代目の松田道彦さん。妻の真理子さんと二人三脚で地域に根づく食文化を伝えています。

▲「おたぐり」は味噌煮タイプ。新鮮な赤色が美しい馬刺は常に切りたてを提供
先代が鯉料理以外の郷土食を始めたきっかけは、中央自動車道の開通(1975年:駒ヶ根IC ~ 中津川IC開通)だったそう。旅人が訪れるようになったことから、より土地らしいものを提供したいと考え、馬刺や蜂の子、ざざ虫などの郷土料理を提供してほしいとの周囲の声に応じました。「おたぐり」も道彦さんの幼少期には店のメニューになかったそうですが、先代が始めたもののひとつです。

▲馬刺や鯉甘煮、蜂の子など、飯田・下伊那の郷土料理や珍味、地元食材が定食で味わえる「伊那香(いなか)定食」。手前が「源助かぶ菜」の漬物
「時代に応じてメニューを変えながらも、地元食材を大切に郷土の味を守ってきました。南信州は食材料が豊富な地。料理人としてはやりがいがありますね」
そんな道彦さんの言葉どおり、店では鯉料理や「おたぐり」、馬刺など土地の味を一度に楽しんでほしいと、定食としても提供。馬刺は鮮度を大切に、信頼のおける取引先から仕入れるなど流通ルートにもこだわっています。また「源助かぶ菜」や「下栗芋」など、地元でしか手に入らない信州の伝統野菜を可能な限り使うことも道彦さんの信念です。
歴史のなかで育まれた食肉文化と郷土の味覚が、地域の魅力となって広がっています。

満津田食堂
住所:飯田市主税町1
電話:0265-22-0437
https://www.matsudashokudou.com/
※この記事は2022年12月時点の情報です。取扱商品等は変更になっている場合がございますので、ご了承ください