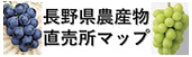投稿日:
更新日:
夜空を赤く染める「野沢温泉道祖神祭り」

温泉とスキーの町、そして野沢菜発祥の地として知られる人口約3,600人の小さな村で毎年1月15日に行わる「野沢温泉 道祖神祭り」。国指定重要無形民俗文化財に指定され、近年は多くの外国人も訪れる日本有数の火祭りです。
約20mのブナを御神木とした社殿をめぐる火の攻防戦、社殿と初灯篭が燃え尽きるクライマックス。圧倒的な迫力で繰り広げられ、奇祭ともいわれるこの祭りは、村を支える人づくりの伝統でもありました。

伝統の火祭りへの誇りがつくる仲間
三夜講を経て強くなる、「野沢の男」としての自覚
北信州では、火の攻防を行う祭りが今もいくつか継承されていますが、野沢温泉のスケールは別格で日本三大火祭りにも数えられます。
祭りの主役は、厄年の42歳を筆頭に41歳と40歳の3年代で構成される「三夜講(さんやこう)」と呼ばれる男衆と同じく厄年を迎える25歳の男衆。特に三夜講は、同じ仲間で3年間祭りを執り行う重要な役目を担います。それは、社殿の御神木の伐採にはじまり、祭りのほぼ全て。これを経験し「野沢の男」であることを強く自覚するのだそうです。

準備の中で最も重要なのが社殿造りと道祖神造り。取材した11月末、42歳と41歳の男衆によって道祖神が製作されていました。
「今の三夜講で祭りを仕切るのは初めてで、中心となるのは僕ら42歳。だから今回は本当に特別です。社殿が立派に組めるか、当日無事に終えられるかなど、伝統を受け継ぐことの重さを感じます」と総括の富井さんは語ります。

四十二歳厄年励翔会 総括 富井義之さん
野沢温泉村出身。25歳厄年では攻防戦を経験し、今回は42歳厄年として祭り全体の作業や段取りなどを取り仕切る総括に。「小学4年の息子は、学年として灯篭を出すんですよ」と父親としての一面も。

村人との絆
道祖神祭りを経験して初めて、一人前の大人になる
祭り最大の見せ場は、25歳厄年の男衆が松の枝で村人の松明の炎から社殿を守るという激しい火の攻防。本気の喧嘩さながらの気迫が伝わってきます。
「髪が燃えたなんて話も聞きますが、これを乗り越えて初めて一人前の大人として認められる。先輩たちの姿は小さな頃からの憧れでしたから、当日が楽しみです」と25歳代表の小林さんは言います。


一方、道祖神委員長を務める42歳の杉山さんは「25歳のときは無我夢中で、やりきったと感動していましたが、全て先輩たちがお膳立てしてくれていたんだと、今の立場になって実感しました。だから今度は、僕らがあの気持ちを味あわせてあげないといけないんです」と語ります。
その勇壮さから世界からも注目を集める道祖神祭りは、村のしあわせを願うと同時に、仲間同士はもちろん、村人との絆をより強くし、故郷への誇り、そして村を背負う人を育みながら紡がれる伝統でもあるのです。

小林文哉さん
25歳厄年の代表として火元もらいを務める。当日はもちろん、準備のために仕事を休んで帰省する同級生も多いのだとか。
信州の冬の祭り&信州の新春の縁起物


【小布施の安市】
町を挙げて行われる小布施最大のお祭り。江戸時代から始まった「六斎市」のなごりと言われ、だるまや縁起物の市で賑わいます。15日の「火渡りの神事」は、安市最大の呼び物。修験者や町長などが次々と火の上を渡ります。なんと一般の方もチャレンジOK。新春に心頭滅却できれば、きっと良い1年が待っているはずです。
1月14日・15日(毎年同日)
皇大神社
小布施町商工会(026-247-2028)


【大網(おあみ)火祭り 】
自然の恵みに感謝し、今年1年がよい年になるようにと雨飾山の神に祈る祭りです。白銀の世界に篝火が灯る空間で、神を迎える巫女の幻想的な舞や神の使いの鬼に扮したふんどし姿の男たちが五穀豊穣を願う勇壮な踊りが見どころ。立春を過ぎたばかりのまだまだ寒さの厳しい時期ですが、躍動する松明の炎が会場一帯を熱くします。
2月第2土曜日(平成29年は2月11日)
大網地区 阿弥陀ヶ原会場
小谷村観光連盟(0261-82-2233)

【芦ノ尻の道祖神祭り】
長野市
1998年の長野冬季オリンピックの開会式にも登場したことでも知られる道祖神。各戸から持ち寄った注連縄を使って道祖神の顔(神面)や供え物を作ることから「神面装飾道祖神祭」とも呼ばれ、毎年独特な顔が誕生します。夜には盛大にどんど焼きが行われ、その残り火でお餅を焼いて食べると1年無病息災に過ごせるといわれています。
◇1月7日(毎年同日開催)/長野市大岡支所 026-266-2121

【信濃国分寺八日堂縁日】
上田市
和唐折衷の美しい三重塔(国重文)がたつ信濃国分寺。八日堂縁日では、本堂で護摩法要やご祈祷が行われ、招福除災の護符「蘇民将来符」や福だるま市も開かれます。500年以上の歴史をもつ蘇民将来符は、7日お昼頃から寺の蘇民将来符が、また8日午前8時からは蘇民講による七福神が描かれた絵蘇民が頒布され、早朝から多くの参拝者で賑わいます。
◇1月7日・8日(毎年同日開催)/信濃国分寺 0268-24-1388

【松本あめ市】
上田市
上杉謙信が敵である武田信玄に塩を送ったという故事に由来し、松本に塩が到着した日を祝って始まったと伝えられ、古くは「塩市」と呼ばれた伝統行事です。中心市街地では、七福神が加わる時代行列、全国あめ博覧会・即売会、塩取り合戦、子供たちの福だるま売りなど多彩な行事が行われ、お正月らしい賑わいを見せます。
◇毎年1月上旬(平成29年は1月7日・8日)/松本あめ市実行委員会事務局(本町商店街振興組合) 0263-36-1121

【新野の雪祭り】
阿南町
雪を吉兆として五穀豊穣を祈願する祭り。1月14日の夜から翌朝にかけ、伊豆神社境内で田楽や舞楽などの日本の伝統芸能の原点ともいえる舞踏が徹夜で繰り広げられます。極寒の真夜中から朝まで、もくもくと松明を焚きながら行われることから「眠い煙い寒い」と表現されますが、それを凌ぐ魅力が多くの人を惹きつけます。
◇1月14日・15日(毎年同日開催)/阿南町振興課 0260-22-4055

【おたや祭り】
長和町
長和町古町の豊受大神宮の例祭で、「旅屋(たや)」のある伊勢社の祭りであることからこのように呼ばれるようになったと伝えられます。境内と町内5カ所の路地に奉納されている、人形のような山車がこの祭りの名物。5つの保存会が昔話、歴史、干支、世相などを題材に毎年趣向を凝らしたものが作られます。
◇1月14日・15日(毎年同日開催)/長和町産業振興課 0268-75-2047

【羽広の獅子舞】
伊那市
約400年の歴史を持つ小正月の伝統行事。口を閉じた雄獅子と口を開いた雌獅子の2頭による舞い合わせは、全国的にも稀有といわれ、雄と雌がそれぞれ別のお囃子に合わせるのも独特です。羽広区の仲仙寺での奉納の後、雌雄の獅子は寺を境に北南に分かれて区内の家をまわり、無病息災などの願いを込めた舞いを披露します。
◇毎年1月15日に一番近い日曜日(平成29年は1月15日)/(一社)伊那市観光協会 0265-78-4111(代)