厳寒の冬が育む 信州伝統の保存食2017.02.24

寒さが最も厳しくなる1、2月の信州。特に盆地や山間部では、夜間はマイナス10℃、日中でも5℃未満という日がほとんどです。しかし、その寒さを逆に利用したのが信州人。夜に凍みさせ、日中に融かす、これを繰り返す天然のフリーズドライ製法で、さまざまな加工品を作ってきました。
寒天やこうや豆腐などは、まさにその代表格。近頃は、その優れた栄養価から健康食材としても注目を集めています。そんな信州の冬がつくる日本が誇る伝統の保存食をご紹介しましょう。

手軽に味わえる利便性と応用力に優れた保存食
厳冬期に手仕事でつくる伝統が詰まった「凍り餅」
戦国の世では、籠城の際の兵糧にもなったという「凍り餅」は、サクサクになるまでお餅を乾燥させた保存食。お湯で戻すだけでも食べられるので、米作地帯である飯島町では、おこびる(農作業の合間の軽食)として重宝されていたそうです。
現在、伊那谷でほとんどつくられることがなくなった凍り餅を復活させたのが、いつわの皆さん。


作業がはじまるのは最低気温が氷点下になる頃。一度ついた餅は、やわらかくなるよう水を含ませて再び杵でつきます。角切りされたお餅は地元のお母さんたちが手作業でひとつずつ和紙に包み、2~3日水に浸してから、約2ヶ月間軒下へ吊るし完全に水分が抜けると完成です。
「前に品切れになった時、ダメもとで夏場につくってみたんです。でも外側だけが乾いて中が乾かない。やっぱり冬じゃないとつくれないと身をもって知りました」と苦笑いする林さん。自慢の餅米で真っ白に美しく仕上がる凍り餅には、伝統とこだわりが詰まっています。
 農事組合法人いつわ(飯島町)
農事組合法人いつわ(飯島町)
代表理事 林英彦さん
平成13年に組合法人を設立。自らが地元で栽培した餅米を使って、凍り餅や大福餅、赤飯など多彩な商品を手掛け地元スーパーや道の駅で販売。料理好きでお餅レシピの考案にも力を入れています。

冬の陽光と寒さでつくる天然のフリーズドライフード
諏訪地域の環境が生みだす究極のスローフード「角寒天」
茅野市をはじめとする諏訪地域で角寒天づくりが始まったのは約180年前。関西へ寒天製造の出稼ぎに出ていた小林粂左衛門が製法を学び、故郷の諏訪でつくり始めたと言われます。
天然製法で角寒天をつくるためには、寒さだけでなく、晴天率が高いこと、雪や風が少ないこと、良質の水に恵まれていることなどの自然条件が必須で、そのすべてを満たす諏訪地域は、国内唯一の産地であるともいわれます。

製造できるのは、12~2月の気温が下がったときのみ。近年は暖冬傾向が続いていることもあり、製造稼働日は実質70日くらいしかないそうです。
「角寒天はやっぱり美しく仕上げたい。ただ凍らせるだけでは曲がったり形が悪くなったりするんです。昼間のおてんとさまで水分を落として夜は凍らせる。これを繰り返すのがきれいにおいしくつくるコツなんです」と語る伊藤社長。角寒天はこの地域の環境だからこそつくれる贅沢なスローフードです。
 北原産業(株)(茅野市)
北原産業(株)(茅野市)
取締役社長 伊藤宗登さん
天草卸商として東京都江戸川区で創業し、1956年には茅野市へ本社を移転して寒天製造を開始。寒天一筋60余年で現在は年間約50万本の角寒天のほか、糸寒天や加工品の寒天飴なども製造。

旨さと栄養としあわせがギュッと詰まった保存食
山あいの暮らしの中に息づく昔ながらの「丸干し凍み大根」
長野市信州新町の山深い小さな集落で暮らす宮尾さんご家族。85歳のご主人、善二郎さんは酪農家と会社勤めを経て、現在は、妻の昌子さんと畑を営んでいます。
宮尾家では昔から大豆や小豆、野菜などは自家栽培が当たり前。冬は畑の仕事と同様に凍み大根などの保存食づくりも手掛けます。「わしらは、自分で作った作物を自分たちが夏場でも食べられるようにしているだけ。それを売って欲しいと言われるなんて、なぁんとも不思議な気分ですよ(笑)」と笑いあう宮尾さんご夫妻。

切干は今でも多く流通していますが、手間ひまのかかる「丸干しの凍み大根」は貴重な食材として直売所でも人気の商品になっています。その栄養価も高く、凍み大根にすることで、カリウム・鉄分・マグネシウムなどのミネラルや食物繊維が生と比べると10倍以上にもなる健康食材。信州の山間での暮らしの中にも、健康としあわせの秘訣がありました。
 宮尾善二郎さん・昌子さん(長野市)
宮尾善二郎さん・昌子さん(長野市)
信州新町出身の仲睦まじいご夫妻。「昔から我が家は賑やかで」と言うだけあって善二郎さんは12人兄弟の長男。現在も息子さんご夫妻と孫3人の7人家族で暮らしています。

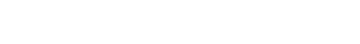 ライフスタイル・オブ・信州
ライフスタイル・オブ・信州


