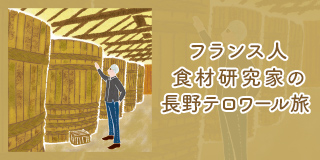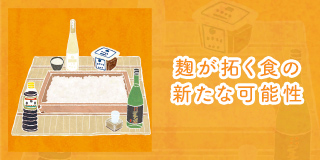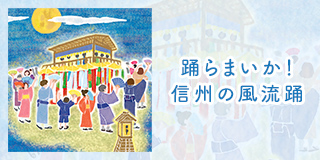信州シルク物語
~繊維のダイヤモンド「天蚕」とは~
2022.01.15
安曇野市天蚕センター/安曇野市天蚕振興会
お話を伺った方:安曇野市天蚕振興会 会長 田口忠志様
長野県内には、駒ヶ根シルクミュージアム(駒ヶ根市)、旧常田館製絲場(上田市)、片倉館(諏訪市)など、かつて各地で繁栄したシルク文化を体感することができる施設があります。そのひとつ、安曇野市天蚕センターを訪ね、安曇野市天蚕振興会の田口会長にお話を伺いました
天蚕(てんさん)て何?
屋内で飼育される蚕を家蚕(かさん)といい、野生のものを天蚕といいます。種類自体が違って、家蚕はカイコガ、天蚕は自然の中にいるヤママユガの幼虫です。家蚕は白い糸が、天蚕からは黄緑色の糸がとれます。
日本固有のお蚕さんで、現在の繭の生産量は全国で十数万個程度。そのうち4万個がこの天蚕センターの関連施設でつくられています。

安曇野市天蚕振興会の田口会長
糸の特徴は?
なんといっても黄緑の光沢ですね。もともとは黄色い色素を持っていて、それが日の光を浴びることで緑色になります。希少な糸で“糸のダイヤモンド”とも呼ばれているんです。扁平で太くて柔らかく、伸縮性があり暖かいのも特徴です。
ほとんどが着物で使われますが、家蚕の糸とは太さも質も違うことを活用して、質感を変えたり細やかな織り柄を出したりとアクセント的な用途に重宝されています。

天蚕生糸

天蚕織り
安曇野で天蚕が盛んになったのはなぜ?
江戸後期に野生の蚕から糸をとろうと雑木林からヤママユガの卵を採取してきて、飼育したことから始まったといわれています。天蚕は雑食で、クヌギ、コナラ、柏などを食べるのですが、一番は北アルプス山麓に豊かなクヌギの林があるので、育成に適していたんでしょうね。明治30年代の最盛期には、800万個の生産量を誇りました。その後、焼岳小爆発の降灰や第二次世界大戦の開戦などの理由で天蚕は、いったん途絶えてしまったのですが、有明の天蚕の文化を復興させようという動きが起き、昭和53年にこのセンターが開設されました。現在、5人の織子が在籍し、伝統と技術を受け継ぐべく、日々機(はた)に向かっています。
地域の人たちに受け継がれてきたこの文化を後世に伝えていくことが、わたしたちの使命。新たな天蚕の価値を作り上げていきたいと思っています。

天蚕アイテム
こんなに違う天蚕と家蚕
| 天蚕 | 家蚕 | |
| 蚕の大きさ | 7〜8㎝ | 約2㎝ |
| 大きさ(繭) | 約6〜8g | 約1.8~2.2g |
| 糸の長さ | 600〜700m | 1,500m |
| 太さ | 5.0〜6.0デニール | 2.8〜3.0デニール |
| 色 | 緑色 | 白 |
| 糸の色 | 黄緑色 | 白 |
※この記事は2022年1月時点の情報です。取扱商品等は変更になっている場合がございますので、ご了承ください

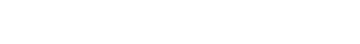 銀座NAGANOのご案内
銀座NAGANOのご案内